妊活がうまくいかない理由は血流不足?鍼灸で子宮環境を整える医学的根拠
妊活に悩む女性の多くが抱える「見えない原因」とは
「病院で検査しても大きな異常はない」
「ホルモン値も年齢の範囲内」
それでも妊娠に至らない――。
このようなケースでは、 「子宮や卵巣の血流不足」 が隠れた原因になっていることがあります。
実は、東洋医学では血液の巡りは卵子の質や子宮内膜の状態に直結し、妊娠率を左右する重要なポイントなのです。
この記事では、
- 妊活と血流の深い関係
- 医学的にわかっている事実
- 東洋医学から見た血流の意味
- 鍼灸で血流を改善できる理由
を詳しく解説します。
なかなか結果が出ずもどかしい思いをしているならぜひ一度今の妊活に
「+鍼灸」という新しい妊活の選択肢を、ぜひ知っていただければと思います。
妊活と血流の関係
子宮・卵巣にとって血流は“生命線”
妊活において「血流」は単なる体の循環の話ではなく、卵子の質や子宮内膜の環境、そしてホルモンの作用に直結する非常に重要な要素です。
1. 卵子の質と血流
卵子は卵巣の中の卵胞で成熟しますが、その発育には酸素や栄養が不可欠です。血液が十分に供給されていないと、卵胞が栄養不足や酸素不足となり、結果的に「卵子の質」が低下するリスクが高まります。
実際に、血流が良い女性の方が「受精卵の分割スピードがスムーズで、胚のグレードが高い」傾向が報告されています。これは、血流によって細胞のエネルギー代謝が円滑に行われるためと考えられています。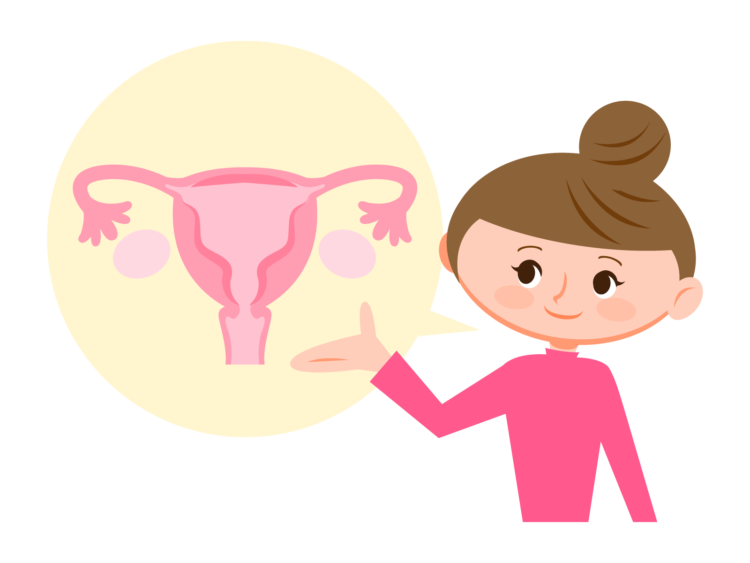
2. 子宮内膜と血流
子宮内膜は受精卵が着床する“ベッド”のような存在です。このベッドがふかふかで温かく、柔らかい状態でなければ、受精卵は定着しにくくなります。
血液がしっかり流れていると、内膜は厚みを増し、血管が豊かに張りめぐらされ、栄養と酸素を十分に受け取ることができます。逆に血流不足になると内膜が薄く硬くなり、着床の確率が低下することがわかっています。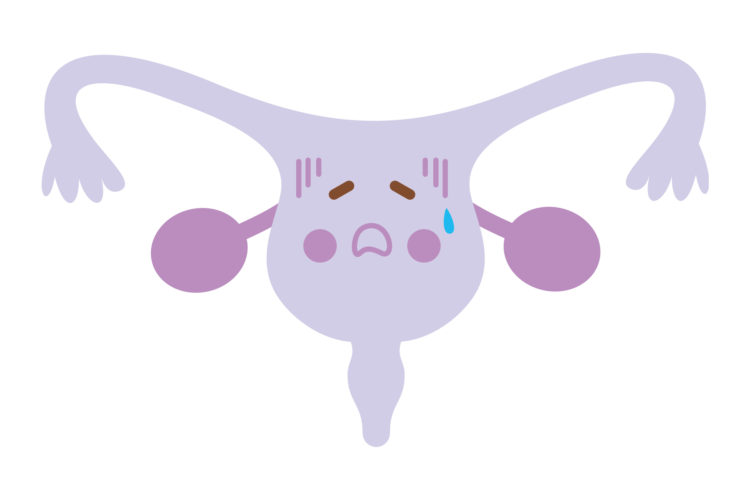
3. ホルモンの作用と血流
エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンは、血液を介して卵巣や子宮に届けられます。
血流が悪いとホルモンが必要な部位に十分に届かず、排卵がスムーズに起こらなかったり、黄体機能不全による高温期の不安定さにつながることもあります。つまり「ホルモンは分泌されているのに正しく作用できない」という状態を招く可能性があるのです。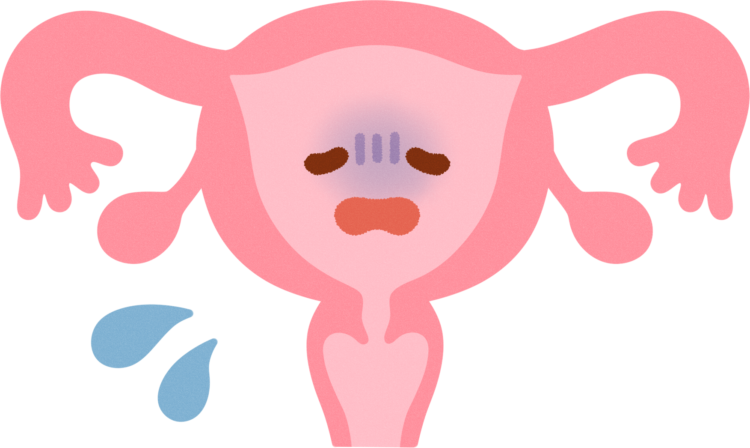
東洋医学の視点からみた「血流と妊娠力」
東洋医学では、妊娠力を「気・血・水」のバランスで考えます。特に「血(けつ)」は子宮や卵巣の働きを支える大切な要素であり、血の不足や滞りは「妊娠しにくい体質」に直結します。
1. 瘀血(おけつ)と妊娠の関係
瘀血とは「血の巡りが滞っている状態」を指します。
症状としては、冷え、月経痛、経血に塊が多い、くすみやシミが出やすい、肩こりや頭痛など。
瘀血があると、子宮や卵巣に必要な栄養が行き渡らず、内膜が厚くならなかったり、卵子の質が低下したりします。つまり、東洋医学でいう「瘀血」は、西洋医学的にいう「子宮・卵巣の血流不足」と重なる概念なのです。
2. 気の滞りと自律神経
「気の流れが悪い」と表現される状態は、現代的にいえば「ストレスによる自律神経の乱れ」です。気の滞りがあると血も動かず、結果として冷えやホルモン分泌の乱れにつながります。妊活中のイライラ、不安、不眠などはこの「気滞」と関係が深いとされています。
3. 血虚(けっきょ)と卵子の栄養不足
血が不足している状態を「血虚」と呼びます。顔色が青白い、めまい、爪が割れやすい、経血量が少ないなどが特徴です。血虚では子宮や卵巣に十分な栄養が運ばれず、卵子が育ちにくく、内膜も十分に厚くならないことがあります。
鍼灸による血流改善の仕組み
では、鍼灸はどのようにして血流を改善し、妊娠力を高めるのでしょうか?
1. 自律神経の調整
鍼灸刺激は自律神経に働きかけ、交感神経と副交感神経のバランスを整えます。これにより血管が拡張し、子宮や卵巣への血流が改善します。
👉 実際に、鍼灸施術後に子宮動脈の血流量が増加したという報告もあります。
2. 局所の血流促進
ツボを刺激することで毛細血管が拡張し、局所的な血流が改善します。例えば「三陰交」「関元」「気海」などのツボは、子宮・卵巣の血流を高める代表的なポイントです。
3. ホルモンバランスの調整
鍼灸は視床下部-下垂体-卵巣系(HPO軸)に働きかけるとされ、排卵や高温期を安定させるサポートをします。血流が改善することでホルモンもスムーズに作用しやすくなるのです。
/
近年の研究でも「血流と妊娠率」の関係が示唆されています
\
1. 子宮血流と妊娠率
体外受精(IVF)の研究において、子宮動脈の血流状態は妊娠成立に直結する重要な因子であることがわかっています。
血流はドプラエコーで「PI(Pulsatility Index:抵抗指数)」として測定されます。PIが高い=血管抵抗が強く、血液がスムーズに流れにくい状態を示します。この場合、子宮に十分な血液が届かず、着床のための環境が不十分となります。
実際、子宮動脈PIが高い女性は、低い女性に比べて妊娠率が有意に低下すると複数の報告があります。さらに、流産率が上がる傾向も指摘されており、「子宮血流は妊娠の継続性にも影響する」可能性があるのです。
2. 子宮内膜と着床
子宮内膜は受精卵が着床するための“ベッド”です。内膜が薄く、血流が悪い状態では受精卵に十分な酸素や栄養を供給できず、着床が成立しにくくなります。
医学的には「子宮内膜の厚みは妊娠率に比例する」とされており、特に7mm未満では妊娠率が大きく低下することが明らかになっています。
さらに、血流が悪いと単に「厚みが足りない」だけでなく、子宮内膜の柔軟性や受容性にも影響を与えます。血管が豊かに走る柔らかい内膜ほど、受精卵を受け入れる力が高いと考えられています。
3. 卵子の質と血流
卵子の質は年齢だけでなく、卵胞にどれだけ良好な血流が届いているかにも左右されます。卵胞は毛細血管のネットワークから酸素や栄養を受け取りながら育ちますが、血流不足の状態では代謝が不十分となり、結果として染色体異常や受精率低下につながる可能性があります。
近年の研究では、血流改善が卵胞の発育を促進し、受精卵(胚)のグレードを上げることが確認されています。さらに、血流の改善は卵子内のミトコンドリア機能を高めるとされ、これは卵子が分裂・発育するための「エネルギー生産力」を底上げすることを意味します。
👉 つまり「卵子の質は年齢だけで決まるものではなく、血流という改善可能な因子にも左右される」という点は、妊活に取り組む女性にとって大きな希望となる事実です。

血流が悪くなる主な原因について
1. 冷え
冷えは妊活世代の女性に特に多い症状です。体温が低下すると末梢血管が収縮し、血液循環が悪化します。特に手足が冷たい「末端冷え性」や、基礎体温が低い「低体温傾向」は、骨盤内臓器(子宮・卵巣)への血流を不足させやすくなります。血流が不足すると、子宮内膜が十分に厚くならず、受精卵が着床しにくい状態を招きます。また、冷えは基礎代謝やホルモン分泌にも影響し、排卵障害や黄体機能不全の一因となることが知られています。
2. ストレス
精神的・肉体的ストレスがかかると、自律神経のうち「交感神経」が優位になり、血管が収縮します。これにより子宮や卵巣といった骨盤内臓器への血流が低下します。さらにストレスは、脳の視床下部に影響し、卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体形成ホルモン(LH)の分泌を乱すことが分かっています。その結果、排卵がスムーズに行われなかったり、月経不順を引き起こすケースもあります。慢性的なストレスは血流を悪くするだけでなく、ホルモンバランスを根本的に乱す要因でもあるのです。
3. 骨盤の歪み・姿勢不良
長時間のデスクワークやスマホの使用で猫背や骨盤の後傾が続くと、骨盤周囲の筋肉が硬くなり、血管やリンパの流れを妨げます。特に仙骨周囲の血流が悪化すると、子宮・卵巣に必要な酸素や栄養が届きにくくなります。さらに、姿勢の崩れによって下半身の冷えやむくみが助長され、慢性的な血行不良につながります。医学的にも「骨盤内うっ血症候群」という疾患があり、骨盤の静脈血流が滞ることで月経困難症や下腹部痛、不妊の原因となることが報告されています。
4. 加齢
加齢によって血管の弾力性が低下し、動脈硬化が進むと、全身の血流が悪化します。特に卵巣は血流の影響を受けやすく、加齢とともに卵巣機能は低下し、卵子の質も下がっていきます。これは自然な生理現象ですが、生活習慣や治療によってある程度サポートすることは可能です。また、卵巣への血流が不足すると卵胞の成長が不十分になり、採卵数の減少や受精率の低下にもつながります。医学的な研究でも、卵巣血流の低下は妊娠率の低下と関連があることが示されています。
東洋医学の視点からみた「血流と妊娠力」
東洋医学では、妊娠の成立には「気・血・水」の調和が不可欠と考えます。特に「血」は、子宮(胞宮)に栄養と温かさを与え、卵子や受精卵の成長を支える重要な要素です。血の不足や停滞は、妊娠力そのものを弱めてしまいます。
1. 瘀血(おけつ)と妊娠の関係
瘀血とは?
「血の巡りが滞っている状態」で、西洋医学でいう「血流障害」に近い概念です。慢性的な冷えやストレス、生活習慣の乱れによって発生するとされます。
瘀血の典型的なサイン
- 月経痛が強い
- 経血に黒っぽい塊が混じる
- 下腹部に刺すような痛み
- 顔色が暗い、唇が紫がかっている
- シミ・くすみが出やすい
- 慢性的な肩こり・頭痛
妊娠への影響
瘀血があると、子宮や卵巣への血流が滞り、十分な栄養や酸素が届きません。結果として…
- 子宮内膜が十分に厚くならない
- 卵胞の発育が不良になり、卵子の質が低下する
- 着床率が下がる
つまり「瘀血=子宮・卵巣の血流不足」という理解が、西洋医学と重なります。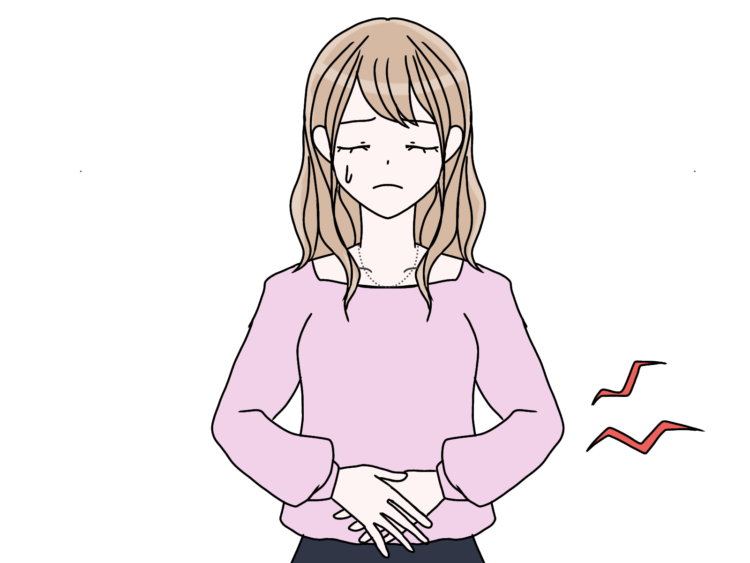
2. 気の滞りと自律神経
気滞とは?
「気の流れがスムーズでない状態」で、現代医学的には「ストレスや自律神経の乱れ」にあたります。精神的緊張や我慢、感情の抑圧が大きな原因です。
気滞のサイン
- イライラしやすい
- 不安・不眠がある
- 胸や喉がつかえる感じがある
- 月経周期が乱れやすい
- 月経前に乳房が張る
妊娠への影響
気が滞ると血流も停滞し、ホルモン分泌にも影響が出ます。具体的には…
- 排卵がスムーズに起こらない
- 黄体機能不全になりやすい
- 月経周期が安定しない
東洋医学では「気は血を動かす」と考えられており、気の流れが滞れば血流も悪化するため、妊娠力低下の大きな要因となります。
3. 血虚(けっきょ)と卵子の栄養不足
血虚とは?
「血が不足している状態」で、栄養不足や過度なダイエット、睡眠不足、慢性疾患などで起こりやすいとされます。
血虚のサイン
- 顔色が青白い・ツヤがない
- めまい・立ちくらみ
- 爪が割れやすい、髪がパサつく
- 経血量が少ない、色が薄い
- 不眠や夢をよく見る
妊娠への影響
血虚では、子宮や卵巣に十分な栄養が供給されません。結果として…
- 卵胞が育ちにくく、卵子の成熟が不十分になる
- 子宮内膜が薄くなり、受精卵が着床しにくい
- 妊娠しても維持しづらい
西洋医学的にみると「鉄欠乏性貧血」や「低栄養状態」に近い概念で、卵子や子宮内膜に必要な栄養が不足している状態に相当します。
✅ まとめると…
- 瘀血 → 子宮・卵巣の血流不足
- 気滞 → ストレス・自律神経の乱れ
- 血虚 → 卵子や子宮への栄養不足
これらはいずれも「妊娠しにくい体質」と深く関わり、東洋医学の治療(鍼灸・漢方)では最も重視されるポイントです。
鍼灸で「血流と妊娠力」にアプローチする方法
妊活中の方にとって、子宮や卵巣に血液をしっかり届けることはとても大切です。東洋医学では、妊娠力を妨げる要因を「瘀血・気滞・血虚」と捉え、それぞれに合わせた鍼灸施術で改善を目指していきます。
1. 瘀血タイプには「血の流れをほどく」アプローチ
瘀血があると、子宮や卵巣に必要な栄養が届かず、着床環境が整いにくくなります。
🔹 鍼灸では:
- 下腹部や足のツボ(例:三陰交、血海、気海)を使って血流を促す
- お灸でお腹や腰を温め、骨盤内の循環を改善
➡ 「生理痛が軽くなった」「経血の色が鮮やかになった」と実感される方も多く、これは血流改善のサインです。血液が巡り出すと、子宮内膜も厚みと柔らかさを取り戻し、妊娠に適した状態に整っていきます。
2. 気滞タイプには「心と体の緊張をゆるめる」アプローチ
気滞は、ストレスやプレッシャーで自律神経が乱れ、ホルモン分泌や血流を妨げている状態です。
🔹 鍼灸では:
- 自律神経を整えるツボ(例:太衝、合谷、内関)を使って気の流れをスムーズにする
- 心地よい刺激でリラックスを促し、交感神経の緊張を解きほぐす
➡ 「施術中にぐっすり眠ってしまった」「気持ちが前向きになった」と言われることが多いのですが、これは血流と気の巡りが整った証拠。ホルモンバランスが安定し、排卵や着床のリズムも改善しやすくなります。
3. 血虚タイプには「栄養と温かさを補う」アプローチ
血虚は、子宮や卵巣に必要な栄養が不足している状態。卵子の発育や内膜形成に直結します。
🔹 鍼灸では:
- 造血を助けるツボ(例:足三里、脾兪、肝兪)で血を補う
- 全身の巡りを整えて「血を作る力」を高める
➡ 「顔色が良くなった」「経血量が増えて周期が安定した」といった変化が見られる方もいます。これは血がしっかり補われ、妊娠力の土台が強くなってきた証です。
鍼灸の効果は「リラックス+体質改善」
病院での治療やサプリメントと違い、鍼灸は「自分の体が本来持っている力」を引き出すアプローチです。
- 血流を促すことで卵子の質をサポート
- 自律神経を整えてホルモン分泌を安定
- 子宮・卵巣に栄養と温かさを届ける
これらを同時に整えられるのが、鍼灸の大きな強みです。
妊活において「血流改善」は欠かせない要素です。
- 瘀血=血の滞りを解消する
- 気滞=ストレスや自律神経の乱れを整える
- 血虚=不足している血を補う
これらを同時にケアできるのが鍼灸の大きな特徴です。
👉 病院の治療や自己流の妊活でなかなか結果が出ない方にこそ、東洋医学的な視点での体質改善をおすすめします。
「体質を変えることは、未来の妊娠力を育てること」。
あなたの体に合わせたオーダーメイドのケアで、一緒に妊娠しやすい体を整えていきませんか?
鍼灸による血流改善の仕組み
「血流を良くすることが妊娠力アップにつながる」とはよく言われますが、実際に鍼灸がどのように血流を改善するのか、本当に効果があるのか、と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
鍼灸は古くから用いられてきた東洋医学的な療法ですが、近年は医学的な研究によっても「子宮や卵巣への血流を改善する効果」が報告されています。ここでは、エビデンスに基づいて鍼灸の仕組みを解説します。
1. 自律神経の調整による血管拡張
血流は自律神経の働きに大きく左右されます。ストレスや緊張で交感神経が優位になると、血管は収縮し、子宮や卵巣への血流が低下してしまいます。
鍼灸刺激は交感神経と副交感神経のバランスを整え、血管の拡張を促すことがわかっています。
📌 研究例
- Stener-Victorinらの研究(2006年, Human Reproduction)では、鍼灸施術によって子宮動脈の血流抵抗指数(PI)が有意に低下し、子宮への血流が改善したことが報告されています。
- この改善は特に体外受精を受ける女性において着床率向上と関連していると示唆されています。
➡ つまり、鍼灸は自律神経を介して「子宮動脈の血流を良くする」効果があると考えられます。
2. ツボ刺激による局所的な血流促進
鍼やお灸でツボを刺激すると、その部位の毛細血管が拡張し、局所的な血流が改善します。特に婦人科領域でよく用いられるのは以下のツボです。
- 三陰交(さんいんこう):足の内くるぶし上に位置し、子宮・卵巣の血流改善に用いられる
- 関元(かんげん)・気海(きかい):下腹部にあり、子宮の働きを高め、着床環境を整える
📌 研究例
- Zhangら(2010年, Fertility and Sterility)は、鍼灸が卵巣局所の血流を改善し、卵胞発育を促す可能性を示しています。
- 実際に、鍼灸を受けた群では卵胞の発育が良好で、採卵数や胚の質の向上が観察されたと報告されています。
➡ 局所の血流改善は「卵子の質の向上」「子宮内膜の厚み改善」に直結します。
3. ホルモンバランスの調整
鍼灸は視床下部―下垂体―卵巣系(HPO軸)に作用することが研究で示されています。HPO軸は排卵や月経周期を調整する中枢であり、ここが乱れると排卵障害や黄体機能不全が起こりやすくなります。
📌 研究例
- Limら(2010年, Gynecological Endocrinology)は、鍼灸がHPO軸に働きかけ、性腺刺激ホルモン(FSH、LH)の分泌に影響を与えることを報告。
- 特に多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性に対し、鍼灸は排卵回復や月経周期改善に有効であったとされています。
➡ 血流改善とホルモン調整の両輪で、排卵から着床までのプロセスをサポートできるのが鍼灸の大きな特徴です。
病院の治療やサプリメントも大切ですが、それだけでは「体質そのものを変える力」までは補えません。
鍼灸は、あなた自身の体に眠っている自然な力を引き出し、
- 子宮・卵巣に血液をしっかり届ける
- 卵子や内膜の質を底上げする
- ホルモンの働きをスムーズにする
といった 妊娠の土台作り を支えます。
👉 「今の自分の体を妊娠しやすい方向に整えたい」
👉 「西洋医学だけでは不安。東洋医学の力も取り入れたい」
そんな方にこそ、鍼灸はおすすめの選択肢です。
———————————–
*鍼灸整体サロンシンヴィア*
———————————–
博多駅より5分!
蔵本ウィメンズクリニックやにしたんARTクリニックからも徒歩5分💕
県外からの来院も多数✨
当院は15年以上、整骨院や鍼灸院、
不妊治療専門クリニックでの経験を活かし、
のべ8万人の施術に携わった
女性鍼灸師による鍼灸整体院です。
・スタッフは全員女性、個室で話しやすい環境を整えています✨
・産科エコー完備で妊娠してからのアフターフォローもばっちり❤
・医療控除対象施設でお財布にやさしい💕
【得意分野】
・生理痛改善
・多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
・婦人科疾患(子宮内膜症、子宮筋腫など)
・妊活(タイミング、AIH、IVF、ICSI)
・自律神経の乱れ
・不眠
・温活
※骨盤矯正はオプションメニューです。
・スタッフは全員女性
・産科エコー完備
・医療控除対象施設
—————————————-
妊活中はもちろん、妊娠初期から鍼灸・整体が受けられる!
妊娠8週からは毎回エコーで赤ちゃんの無事を確認!
つわりの改善もおまかせ!
*鍼灸整体サロンシンヴィア*
https://shinvier.com/web_reservation
公式LINEご登録でお得なクーポンget♡
キャンセル待ちや当日予約のお問い合わせなどもお気軽にどうぞ!
https://line.me/R/ti/p/%40zwn2565d![]()